名前で二度見してしまいますが、この学名はわざと日本語ウケを狙ったものではありません。にもかかわらず、日本語話者には「ボッキ」「チンチン」の連想が強烈すぎて、どうしてもクスッと来てしまう。ここがまず一つの魅力です。実際の語源はラテン語で、種小名 tintinnabuliferum は「tintinnabulum(鈴)」+「‑fer(〜を持つ)」という構成。つまり「鈴を持つ者」という真っ当な意味合いなんですね。また、日本語版ウィキペディアには分布や形態、命名の背景が整理されており、話題化の経緯(日本のラジオ番組等で取り上げられた例)も記録されています。
どんな昆虫?—分類・サイズ・“謎構造”の外見
ボッキディウム・チンチンナブリフェルム(Bocydium tintinnabuliferum)は、カメムシ目ツノゼミ科(Membracidae)の一種。体長は約5mmの超小型。頭上(正確には前胸背=第一胸節)から、柱状の突起が上へ伸び、先端で枝分かれ(計5枝)します。前方の枝の先には小さな球状構造が付き、側方の枝は途中に球を挟んで先端が尖る、後方の枝は腹面を越えて伸びる——という、見れば忘れない造形。色は光沢のある黒い“ヘルメット”+褐色の鞘翅+オレンジ色の腹部に黒点というコントラストで、写真映えは満点。1832年にLesson(ルネ=プリムヴェール・レッソン)が記載した、由緒ある“変な見た目”の昆虫でもあります。
ウィキペディア
どこにいる?—ブラジル東部の森でひっそり生活
分布はブラジルのバイーア州・エスピリトサント州(Conceição da Barra, Santa Teresa)・リオデジャネイロ州。生態は未解明な点も多いのですが、若虫・成虫ともに葉裏で樹液を吸い、夜間は人工光に誘引されることもあると整理されています。日本国内でお目にかかる機会はまずありません。
“ヘルメット”は何者?—ツノゼミに共通する超進化
ツノゼミ類の奇抜な突起は、背中の“ヘルメット”(拡張した前胸背=pronotum)が変形したものと理解されてきました。進化発生学ではこの由来をめぐり議論があり、「翼の連続相同(serial homology)」仮説(= ヘルメットは胸部の別セグメントにある翼に相同性を持つ付属肢様の構造)を支持する研究がある一方、形態学の立場から異論(翼とは相同でない)が出され、のちのトランスクリプトーム解析では「ウィング遺伝子ネットワークの取り込み(co-option)」を支持する報告も登場——と、学術的にも奥が深い分野です。いずれにせよ機能面では、捕食者忌避・カモフラージュ・他種(アリ等)との関係でのシグナルなどが挙げられます。
アリと蜜の「持ちつ持たれつ」—ハニーデュー取引の現場
樹液を吸う半翅目(カメムシ目)では、“ハニーデュー”と呼ばれる糖液を分泌します。これにアリが列を成して“回収”し、代わりに捕食者からツノゼミを守る——この相利共生は熱帯林で日常的に見られ、局所的な食物網をガラッと変えることが知られています。場合によっては、アリの行動が活発化し、同じ植物上の他の草食者や捕食者の数・ふるまいまで変えてしまうことも。
フィールドの観察例では、アリがツノゼミをやさしく触角で“なでる”→ツノゼミがハニーデューを分泌→アリが“お礼に護衛”という一連の流れが記録されています。栄養価や“どの相手か”の識別が取引の安定性を左右する、という近年の報告も。
バズる画像の多くは“近縁種”という罠
SNSや動画で見かける“空飛ぶヘリのローターみたいな頭”の超有名画像は、近縁の Bocydium globulare(通称ブラジリアン・ツノゼミ)であることがしばしば。どちらも同じBocydium属のツノゼミで、球状の突起を備える点がそっくりなため混同されやすいのですが、学名や形状細部は別物です。globulare は“globe(球)を持つ”という名が示す通り、球の印象がより強く、写真資料・動画も圧倒的に多いため、ネット上ではこちらが“アイコン種”になっています。学名や分布をチェックしつつ、“本家” tintinnabuliferum の情報も丁寧に追うのがコツです。
名前は笑える、でも観察は真剣
ここまで見てきたように、名前は日本語的に“ちょっとお茶目”でも、形態・進化・生態は極めてマジメで魅力的。特にツノゼミ全般に共通する“振動コミュニケーション”(植物体を伝わる微振動でやり取りする)やアリとの相利関係(ハニーデューと護衛の交換)は、ボッキディウム属の理解にも役立ちます。後編では、この振動コミュニケーションやアリ共生の仕組み、そして日本での“名前バズ”の具体的エピソードを掘り下げ、写真や動画の“見分け方”までガイドします。
植物を伝う「無音の会話」って何?—振動コミュニケーションの仕組み
ツノゼミの多くは、腹部を小刻みに震わせて植物体に振動を送り、茎や葉を“伝声管”のように使って会話します。人間の耳にはほぼ聞こえませんが、彼らには“音楽”のように世界が鳴っている。研究では、求愛・位置知らせ・採餌の合図などに使われ、同一株内の1–2m程度の近距離でやり取りされることが多いと示されています。大学の研究チームは、ギターのピックアップのようなセンサーでその信号を可視化しており、「人間の音声世界に相当するのが彼らの振動世界」と表現します。
この“植物ネットワーク”の強みは、風や雑音の少ない時間帯(早朝など)ほど通信品質が上がること。野外再生実験でも、その条件を選ぶことで親子間の合図や群れの協調行動が安定することが示されています。
“ヘルメット”は翼の仲間?—進化の議論をやさしく
ボッキディウム属を含むツノゼミの象徴は、前胸背(プロノータム)が変形した“ヘルメット”。その起源をめぐっては、進化発生学で「翼の連続相同(T1に現れた翼の“相同構造”)」を示す研究と、「翼とは相同でない」という反論が続いてきました。2011年の研究は「ヘルメットは翼の系列相同で、関節様の構造や発現遺伝子が翼に似る」と主張し、のちのトランスクリプトーム解析でも“翼パターン形成遺伝子の共用(co‑option)”が支持される一方、形態学の立場から否定的見解も提示されています。最新レビューでは、“翼遺伝子ネットワークの取り込み”という折衷的な見方で整理されつつあります。——要するに「翼の設計図を流用して、でも翼そのものではない“3Dアート”を作った」くらいに理解すると、専門外でもイメージしやすいはず。
よくある誤解:バズってる“ヘリのローター頭”は別種のことが多い
SNSで拡散する“黒い棒に球が4つ・5つ並ぶ”有名カットの多くは、ブラジリアン・ツノゼミ Bocydium globulare。本稿のボッキディウム・チンチンナブリフェルム B. tintinnabuliferumとは同属だが別種です。学名表記や分布、資料の出典を確認すると取り違えを防げます。標本・画像データベース(BOLD Systems)や百科事典系のページで“tintinnabuliferum”の綴りをチェックすると精度が上がります。
観察&検索のコツ—「見分けポイント」ワンポイントだけ
- tintinnabuliferum の資料を探す時は、“Lesson 1832”の名とともに検索すると古い図版(Wikimediaなど)に当たりやすい。
- バズ画像は“Brazilian treehopper”=globulareである確率が高い。“Bocydium tintinnabuliferum image”のように学名フル+“image/illustration”で搾り込む。
- 生態・行動は属や近縁種の知見(振動通信・アリとの相利関係)も参考に。専門レビューや大学サイトが信頼度高め。
まとめ
名前は日本語的に笑えるけど、中身は研究価値の高いマジメな昆虫。
見た目のインパクト+名前のユニークさで、人々の興味を科学に引き込む「きっかけ昆虫」と言える。
本記事おおまかな概要:「ボッキディウム・チンチンナブリフェルムって何?」
- 名前で二度見
- 学名:Bocydium tintinnabuliferum(和名:ヨツコブツノゼミ)
- ラテン語で「鈴(tintinnabulum)を持つ(-ferum)」という意味。
- ところが日本語だと「ボッキ」「チンチン」に聞こえてしまい、ネットやSNSで笑いを誘う存在に。
- 昆虫としての正体
- カメムシ目ツノゼミ科、体長はわずか5mmほど。
- 背中の「ヘルメット(前胸背)」から5本に枝分かれした奇妙な突起が伸びる。
- 分布はブラジル東部。日本では生息しない。
- 突起の機能は未解明だが、捕食者忌避やカモフラージュなどが考えられている。
- 生態と行動
- 植物体に振動を送り合って“無音の会話”をする(振動コミュニケーション)。
- 樹液を吸い、糖液(ハニーデュー)を分泌。これをアリに提供し、その代わりに捕食者から守ってもらう「共生関係」がある。
- 熱帯林の食物網に大きな影響を与える存在。
- 進化の謎
- 背中の「ヘルメット」は、かつての“翼の設計図”を流用した器官という説が有力。
- ただし完全な翼ではなく、昆虫進化学の議論はまだ続いている。
- ネットでの誤解
- バズっている“ヘリコプター頭の画像”の多くは近縁種 Bocydium globulare。
- tintinnabuliferum と混同されがちなので、学名で調べるのが正解。



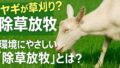
コメント